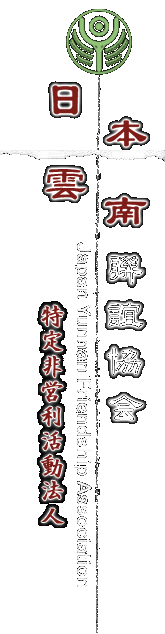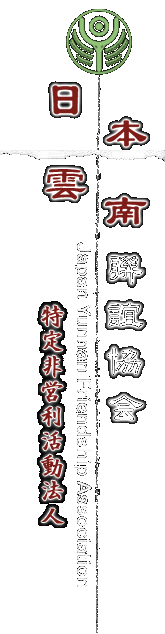|
 |
子どもたちに衛生的で安全な環境を! |
協会が支援する小学校のほとんどはアクセスが困難な僻地にあり、上下水道などの公共施設の整備が遅れています。安全な飲料水の確保が難しかったり、トイレが自宅にある家庭もまだまだ少数です。きちんとしたゴミ捨て場がなく、ゴミが路上や河川などあらゆるところに捨てられていたり、家畜の糞尿で道路や排水溝が塞がれているなどの劣悪な光景も見られます。
また、手洗いの習慣がない、家畜が人と同じ屋内に生活している、トイレの使い方が汚いなど、生活習慣や衛生観念上の問題もあります。小学校では、手洗いやうがいといった衛生習慣を指導してはいるのですが、実際には手洗い場がないなど、指導を実践できる場がありません。
このような環境では、ネズミやゴキブリ、ノミなどが大量に発生したり、食中毒や寄生虫症などの病気が起こる危険性が非常に高く、子どもたちが安全で衛生的に勉強できる環境とは言いがたい状況です。
 |
 |
給食を食べる子どもたち
食堂はなく地面に座り犬と一緒 |
路上では家畜とゴミが
混在している状態 |
 |
 |
衛生的な水の確保は重要 |
村の共同トイレ
小学校のトイレとして使用することも |
 |
 |
プロジェクトの主役は現地の人々 |
地元の住民や中国政府からも、このような状況を改善したいとの声が上がっていますが、そのためにはハード面を整備するだけではなく、現地で生活する一人ひとりの意識と行動を変える必要があります。
そこで協会では、雲南少数民族地域での学校を中心とした健康・環境衛生改善プロジェクト「100万回の手洗いプロジェクト」に取り組むことになりました。
このプロジェクトは、子どもたち、先生、親、村人がプロジェクトの主役となって、小学校の環境衛生の改善と彼ら自身の健康・衛生に対する対処能力を向上させ、協力しながら住みよい環境を作っていくことに重点を置いた事業です。
 |
 |
現地調査実施 |
2007年末、協会は公衆衛生の専門家である薄田榮光氏と共に、支援した3つの小学校を含む雲南省の各地を訪れました。現地のハード面の調査や教師・住民の衛生意識、課題・ニーズの基礎情報収集などを行ない、その他、可能な改善アプローチや関係者の役割や関わり方なども検討されました。
 |
 |
健康や保健衛生に一番関心があるのは
家庭を守るお母さんたち
|
学校の先生、村委員会の人たちから
現地の生の声や要望を聞きます |
 |
 |
主な活動内容と期待される成果 |
この健康・環境衛生改善を目的とした100万回の手洗いプロジェクトは、以下の5つの活動を中心に、2年間にわたって行なう予定です。
これらの活動は当協会単独ではなく、 中国政府機関、現地NGO、公衆衛生の専門家、学校と村民と連携して進めていくものです。私たち協会の役割は、 地元の先生や指導者層が、自らプロジェクトを進めていけるよう背中を
押すことです。
対象校は当協会が支援する第4、6、11校目の小学校地域(建水県岔科鎮白云村小学校学校圏、福貢県匹河郷果科村小学校学校圏、福貢県架科底郷阿達村籐誼小学校学校圏)。その後は、学校建設計画の当初からこのプロジェクトを盛り込んで、全ての支援小学校で実施していきたいと考えています。
Q:どうして100万回なのですか?
A:初回モデル校となる地域の生徒たちが、手洗いを1日2回、2年間
実施すると約100万回になります。手洗いの習慣化を第1段階と
して、徐々に衛生教育を根付かせていくことを目指しています。 |
■□■100万回の手洗いプロジェクト 5つの活動■□■
① 学校の先生・学校保健関係者を対象とした指導力向上のための
研修
② 学校のトイレ施設改修(現在ある貯水施設の改善や手洗い場設
置学校トイレバイオガス化)
③ 小学校での保健衛生教育の授業を使った「ポスターコンクール」
パネルシアターや歌による「手洗いキャンペン」実施
高学年児童から低学年児童への『仲間教育」の導入
④ 学校と村を結ぶ③のコンクールや手洗いキャンペーンの実施
⑤ プロジェクトで培った技術や資料を他の地域のために生かす資源
センターの構築
|
 |
|
子どもたちが健康的に
勉強できますように |
歯磨きも大切な衛生習慣
|
|